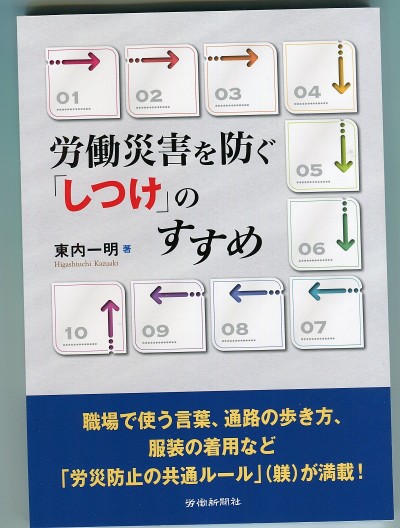|
|
「老子」金谷治著 金谷氏自らの解説文から一部引用します。
◇自分のしていることが本当に人びとの幸福に役立っているのか、そのことを反省してみようともしない知識人たち、私欲をとげるために、文化の名によって横暴な圧力を加える権力者たち、そして、それに追随して盲目的に文化を礼賛する多くの人々、すべて文化の発達した社会にみられる現象である。
そんなことで世界がよくなるはずはない。
人びとは知恵をみがいてずる賢くなり、新しい利益を得るためには平気で人を欺き、欲望は次々と起こって他人を顧みる余裕もない。
世の中が忙しく回転して知識や欲望のとげられていくことが、進歩であり幸福への道であると信じられている。
果たしてそれでよいのか(中略)
老子はそうした不幸な事態を、もちろん漠然とした形においてではあっても、すでに予見したのだといえる。
文化を作りあげておし進める人間の知識と欲望に対して、老子は強く反発する。
「無知無欲」であれ、「無為」であれと、老子は主張する。
自然に帰って本来の自己を発見せよというのである。
◇「上善は水の如し」--最高の善とは水のはたらきのようなものだと、老子は水の徳をたたえる。「水は万物のために役立ちながら、競い争うことがなく、人びとがさげすむ低い場所にとどまっている。そこで、「道」のはたらきにも近い」(第8章)
万物の生長を助ける大きな役割を果たしながら、それはわたしがしたことだといって高みに上るようなことをしない。
低いほうへと流れてさりげないようすでいる。
ここが模範にしたいところである。
「功成りて居らず、--立派な成果があがっても、その栄光に居すわらないーー」(第2章)、「仕事をやりとげたなら、さっさと身をひいて退く」(第9章)、それが処世上の理想とされている。水はその規範であった。
水の徳としては、またその柔弱が賛美されている。「天下に水より以上に柔軟で弱々しいものはないが、それでいて堅く強いものを攻撃するには、これに勝るものはない。柔弱はかえって剛強に勝つのだ」という(第78章)
肩をいからせた突っぱりは強そうにみえるが、実はもろい。
身構えをして人を威圧して、その上に出ようとするような強ばった姿勢では、やがて破滅と死が待ちうけるだけである。
「堅強者は死の徒」である。そして、「柔弱者は生の徒」、柔らかい草木の芽が新しい生命にあふれているように、柔軟な弱々しいものこそが生きのびるのである(第76章)
|
|