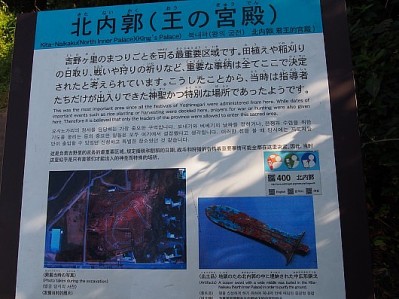|
|
安部龍太郎氏の最新刊「女の城」を読みました。
3つの短編からなっていいて、いずれも戦国時代です。
1つ目は奥美濃の岩村城(別名霧ヶ城)を守る織田信長のおば珠子の物語。
(あらすじは省略)
2つ目は名門畠山氏の側室佐代の物語。
七尾城主畠山氏の勢いに陰りが出はじめ、世にいう畠山七人衆と呼ばれる七人の重臣が力を蓄えていた。中でも守護代家の遊佐氏、佐代の実家温井氏、穴水城主長氏が有力者で互いに権謀術数を駆使し政争と内乱を繰り返していた時代です。一方、外部からは上杉、織田が互いに勢力を伸ばそうとします。かような戦国の世をたくましく生きた佐代の物語です。途中、七尾出身の長谷川等伯が出て来たりします(安倍氏は久留米の出身ですが、長谷川等伯をテーマにした「等伯」で直木賞を受賞しています)。
「満月の城」と題したこの短編が一番気に入りました。
3つ目は「湖上の城」という題名にもあるとおり、浜名湖の近くの井伊谷の城主井伊家の女城主奈美『親族である虎松(後の井伊直正)の後見役』の物語です。
浜名湖周辺の遠江は甲斐の武田、尾張の織田、駿府の今川、三河の徳川の勢力がぶつかるところ。尼僧から女城主に担ぎ上げられた奈美も戦国時代に翻弄される女性です。
しかし、奈美は自分が正しいと思う道を生きた女性としてえがかれていました。
奈美は三方が原の戦で武田信玄に大敗を喫した、徳川家康の大人の風格を見抜き、家康に味方することに決め、後の井伊家の礎を築きます。
|
|